伊藤彰信(日中労交会長) 中国人原爆犠牲者追悼式が7月6日(日)10時30分から、長崎平和公園の中国人原爆犠牲者追悼碑前で行われました。「浦上刑務支所・中国人原爆犠牲者追悼碑」維持管理委員会と長崎の中国人強制連行裁判を … 続きを読む 長崎・中国人原爆犠牲者追悼式


伊藤彰信(日中労交会長) 中国人原爆犠牲者追悼式が7月6日(日)10時30分から、長崎平和公園の中国人原爆犠牲者追悼碑前で行われました。「浦上刑務支所・中国人原爆犠牲者追悼碑」維持管理委員会と長崎の中国人強制連行裁判を … 続きを読む 長崎・中国人原爆犠牲者追悼式

伊藤彰信(日中労交会長) 今年の花岡は、3日間のスケジュールが組まれました。6月28日(土)は、午後からフィールドワーク。29日(日)は、10時から16時まで「中国人強制連行6.30フォーラムin大館」が開かれ、夜は歓 … 続きを読む 花岡事件80年の集会と慰霊式

南京祈念館から南京国際平和通信 第66号(2025年4月)が送られてきました。 南京国際平和通信第66号はこちらをクリックしてください。 □アメリカから日本軍の南京暴行資料を寄贈した 5 月 9 日、アメリカ華人魯照寧氏 … 続きを読む 南京国際平和通信 第66号(2025年4月)

伊藤彰信(日中労働者交流協会会長) 中国の敦煌で、5月30日、31日の両日に開かれた「第4回文明交流・相互参照対話会」に、日中労働者交流協会から私と有田純也(日中労交事務局次長、新潟県平和運動センター事務局長)が参加し … 続きを読む 「第4回文明交流・相互参照対話会」に参加して

■「南京大虐殺犠牲者清明節追悼式典」開催■イギリス元国際兵士ジョージ・ホッケー氏の子孫が来訪■南京大虐殺生存者の子孫が来館し、家族の物語を語る■お別れ 逝去した南京大虐殺生存者4 人の消灯式を行った■中日の紫金草合唱団が … 続きを読む 南京国際平和通信第65号(2025年3月)

「中華全国総工会設立100周年祝賀大会ならびに全国労働模範・先進工作者表彰大会」が28日、北京の人民大会堂で盛大に開催され、習近平中共中央総書記(国家主席、中央軍事委員会主席)が出席して重要演説を行った。新華社が伝えた。 … 続きを読む 中華全国総工会設立100周年祝賀大会

南京紀念館から南京国際平和通信第64号が届きました。南京国際平和通信第64号は、こちらをクリックしてください。 ■お別れ 南京大虐殺の生存者易蘭英さんと陶承義さんが逝去■彫刻家の呉顕林さんが死去■国際ボランティアが南京の … 続きを読む 南京国際平和通信 第64号

新たな50年へ出発を誓う 日中労交の2025年度総会が4月6日(日)午後、東京都大田区で開催されました。 あいさつに立った伊藤会長は「昨年は日中労交50周年事業をやりきった。これからは日中労交の活動をどう継承していくの … 続きを読む 2025年度総会を開催

南京紀念館から南京国際平和通信第63号が送られてきました。 南京国際平和通信第63号はこちらをクリックしてください。 ■ 国際ホロコースト記念日 記念館がグローバルイニシアチブを発足 ■ 旧正月の前、記念館が南京大虐殺生 … 続きを読む 南京国際平和通信第63号
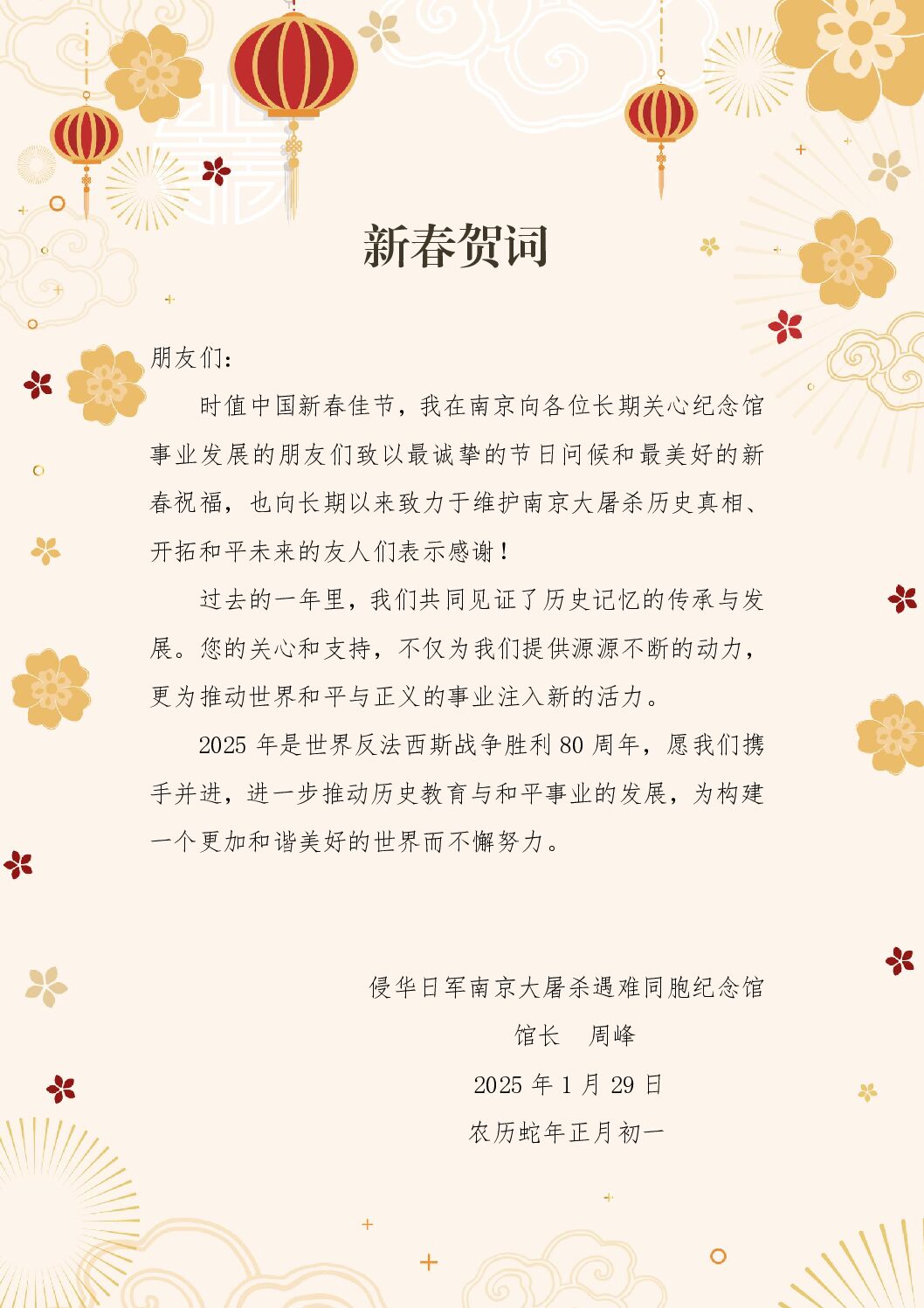
1月29日は旧暦の正月「春節」です。南京紀念館の周峰館長から春節のメッセージが届きました。訳文は以下のとおりです。 ご友人の皆様: 当館の発展にご支持する全ての方々に感謝致し、春節のお祝いを申し上げます。 過去一年、私た … 続きを読む 新春お祝い