伊藤彰信(日中労働者交流協会会長) 中国の敦煌で、5月30日、31日の両日に開かれた「第4回文明交流・相互参照対話会」に、日中労働者交流協会から私と有田純也(日中労交事務局次長、新潟県平和運動センター事務局長)が参加し … 続きを読む 「第4回文明交流・相互参照対話会」に参加して


伊藤彰信(日中労働者交流協会会長) 中国の敦煌で、5月30日、31日の両日に開かれた「第4回文明交流・相互参照対話会」に、日中労働者交流協会から私と有田純也(日中労交事務局次長、新潟県平和運動センター事務局長)が参加し … 続きを読む 「第4回文明交流・相互参照対話会」に参加して

新たな50年へ出発を誓う 日中労交の2025年度総会が4月6日(日)午後、東京都大田区で開催されました。 あいさつに立った伊藤会長は「昨年は日中労交50周年事業をやりきった。これからは日中労交の活動をどう継承していくの … 続きを読む 2025年度総会を開催
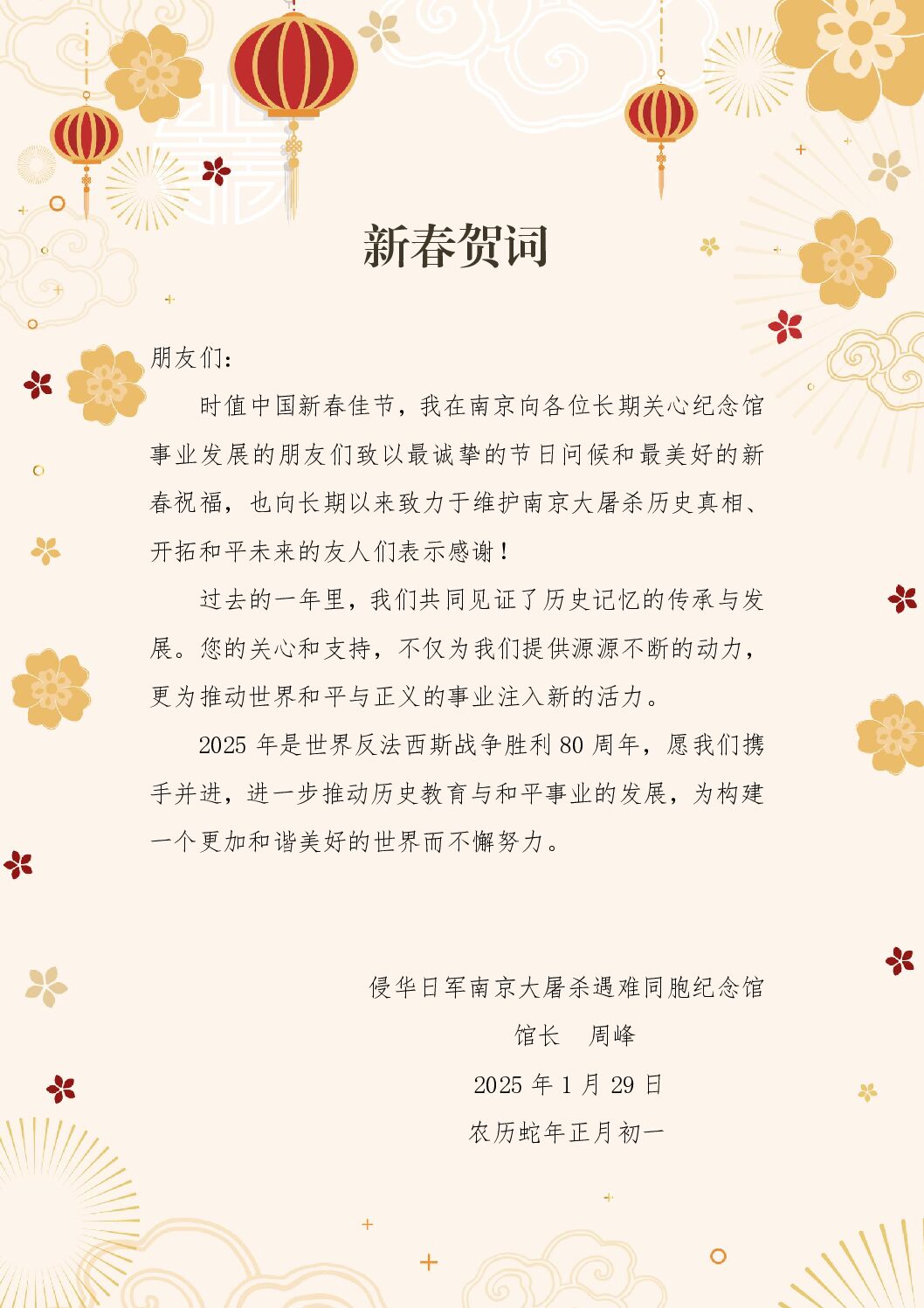
1月29日は旧暦の正月「春節」です。南京紀念館の周峰館長から春節のメッセージが届きました。訳文は以下のとおりです。 ご友人の皆様: 当館の発展にご支持する全ての方々に感謝致し、春節のお祝いを申し上げます。 過去一年、私た … 続きを読む 新春お祝い

日中友好の思いを南京から 伊藤彰信(第9次訪中団団長) 2014.12.19 第9次「日中不再戦の誓いの旅」は12月12日から15日までの4日間、南京を訪問しました。南京大屠殺死難者国家公祭に参加するとともに、侵華日軍 … 続きを読む 第9次「日中不再戦の誓いの旅」
伊藤彰信(日中労交会長) このたび、中国国際交流協会のご招待により、9月2日から6日までの5日間、中国を訪問し、北京、福州、泉州を訪問してきました。訪中団は、日本NPO法人世界、日中友好協会、ベルボ会、国際IC日本協会 … 続きを読む 訪中報告2024.9.2~9.6
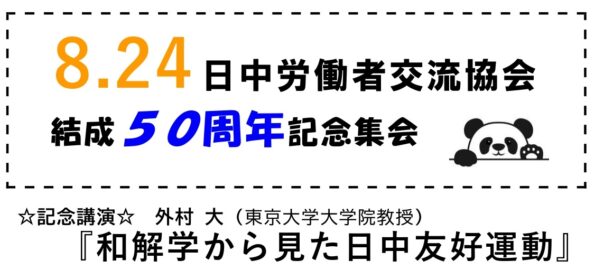
会場のアルバム写真はこちらから 日中労働者交流協会結成50周年記念集会が、2024年8月24日(土)午後、東京都内のホテルで開催され、50名が参加した。 はじめに、「日中労交50年の記録」として「南京に『日中不再戦の … 続きを読む 日中労働者交流協会結成50周年記念集会を開催(報告)

日中労交結成50周年記念集会の報告 「日中労交50年の記録」資料(中国職工対外交流センターからのパンダ皿、南京紀念館の本、バッジや日中労交の機関紙など)の展示と中国中央テレビ局の取材 「日中労交50年の記録」スライド上映 … 続きを読む アルバム日中労働者交流協会結成50周年記念集会

日中労働者交流協会は結成50周年を記念して、「和解から友好へ—日中労働者交流の新しいチャンス」をテーマに、下記のとおり集会を開催します。 ○日 時 2024年8月24日(土)13時30分〜16時50分○場 所 アジ … 続きを読む 日中労働者交流協会結成50周年記念集会
「日中労働者交流協会50年のあゆみ」を発刊しました! 注文受付中 日中労働者交流協会(日中労交)は、1974年8月21日、総評系産別24単産、9地県評、同盟系産別1単産、中立労連が結集してつくられました。初代会長は市川 … 続きを読む 日中労交結成50周年記念
伊藤彰信 日中労交の2024年度総会が4月27日に東京・蒲田の日港福会館で開かれました。 伊藤会長あいさつ 伊藤会長は「日中労交の現在の最大の課題は『台湾有事』を阻止することである。安保三文書によって、中国を仮想敵国 … 続きを読む 日中労交2024年度総会報告